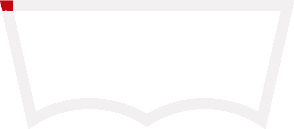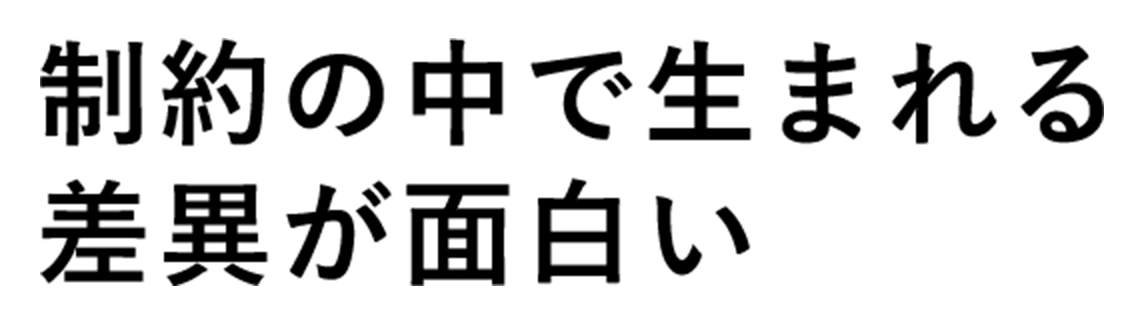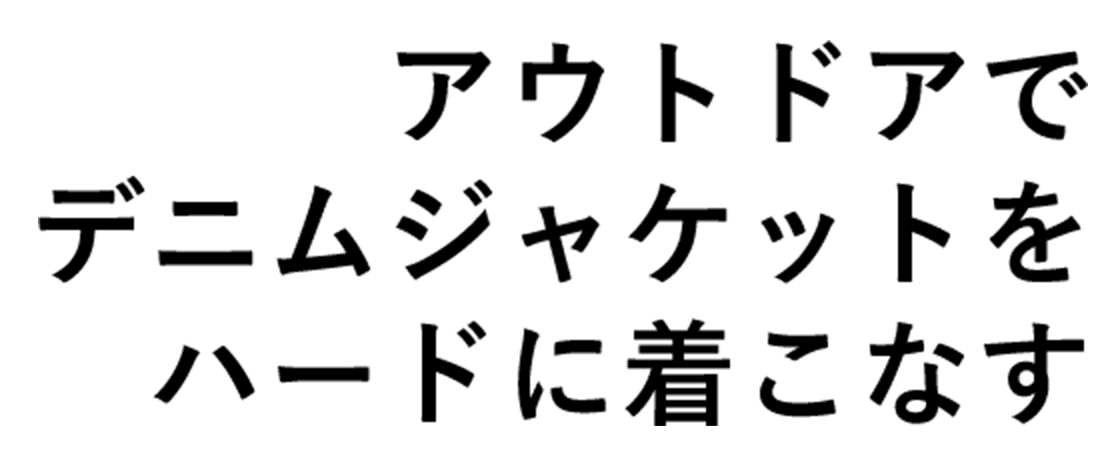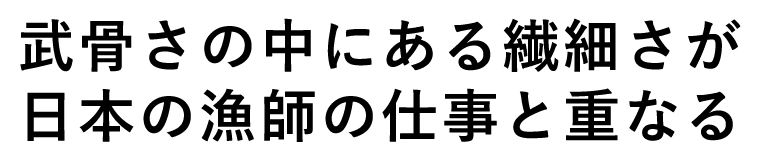建築家
長坂常氏が語る
MADE IN JAPAN™ COLLECTION」の魅力
集合住宅や戸建住宅のリノベーション、「ブルーボトルコーヒー」をはじめとした数々の店舗の設計を手がけ、近年では東京都現代美術館のサイン什器・家具のデザインも担当した建築家・長坂常氏。ジーンズならではの素材感と普遍的なデザインは、彼の唯一無二の感性にも響いたようです。なぜ長坂氏はジーンズを履くのか? なぜジーンズに魅力を感じるのか? その理由を語っていただきました。
「子供の頃は毎日半ズボンを穿いていました。初めてジーンズを穿いたのは林間学校に行った時です。少し硬くて窮屈に感じましたが、少し大人になったような気がしたのを覚えています。ファッションとしてジーンズを意識するようになったのは高校生の頃。映画『トップガン』でトム・クルーズが穿いていたジーンズに憧れて、持っていたジーンズを自分でストーンウォッシュをかけて色落ちさせようとして大失敗しました(笑)。
大人になってからは、リーバイスの『505™』を愛用してきました。ややゆとりのあるシルエットが穿きやすくて気に入っています。僕にとってジーンズは、新しくなって欲しくないものなんです。他のウェアは流行によって大きくデザインが変わりますが、ジーンズに限ってはそういうことがありませんし、僕自身、奇抜なジーンズを穿きたいとは思いません。僕がジーンズに求めるのは、新しさではなく、ずっとスタンダードであることです」
・2021年ミラノサローネに出展したSENBANの3シリーズに加えて、レンガを用いて製作したSENBAN4。http://schemata.jp/senban-salone-del-mobile-2021/
「ジーンズを穿く時は、不思議とジーンズに近い色合いのトップスを合わせることが多いです。他のパンツを穿く時はいろんな色のシャツやTシャツを着るのですが、ジーンズを穿いた時だけは同系色で合わせる方が落ち着くんです。考えてみると、僕はジーンズを素材として捉えているのかもしれません。
例えば、ウッドという素材は、ベージュの素材色と木目や質感などのテクスチャーから成り立っています。それと同様に、色素で染めた布というより、インディゴの素材色と独特の風合いを持った素材としてデニム生地を認識している。僕は内装をデザインする時に、ウッド、砂壁、FRPという異なる素材を組み合わせつつ、ウッドの素材色であるベージュに色味を統一するという手法を使って質感の違いを見せることがあります。ジーンズを穿いた時のコーディネートでも、無意識のうちに同じトーンのアイテムを合わせることで素材の持ち味を楽しんでいるのかもしれません」
・ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展を通じて考案した、丸鋸を用いた旋盤加工。
http://schemata.jp/the-17th-international-architecture-exhibition-the-japan-pavilion/
「『MADE IN JAPAN™ COLLECTION』の『511 ™ SLIM』を穿いていますが、とても柔らかくて快適ですね。今までは少し硬めのジーンズを穿いていたので、馴染むまでに時間がかかるかと思っていたのですが、すでに違和感がありません。以前に一度、日本のジーンズ工場を訪ねたことがあるのですが、旧い機械を直しながら使ってジーンズを作っている様子を見て、その世界観に感銘を受けました。
先ほど、ジーンズはスタンダードであり続けて欲しいと言いましたが、ジーンズという形の決まったレンジの狭いフォーマットの中でアップデートを繰り返していくのは面白い作業だと思います。僕はスタッフにものづくりについて伝える時によく洋服を例に出すんです。パンツは足を通す部分が必須で、ポケットやボタンの位置などの大体の構成は決まっている。しかし、決められた中で様々なデザインのパンツが生まれている。だから、例えば椅子を作る時もこれまでにないような奇抜な椅子を作ろうとしなくても、脚が4本あり、背もたれと座面があるという基本的な構成の椅子でも十分に勝負できるんじゃないかと。
制約があるからこそ、その中で違うことをやるとなるほどと感心される。ジーンズも変わらないルールの中で、少しの差異で人々の気を留めていく。『MADE IN JAPAN™ COLLECTION』にもそうしたものづくりの面白さを感じます」